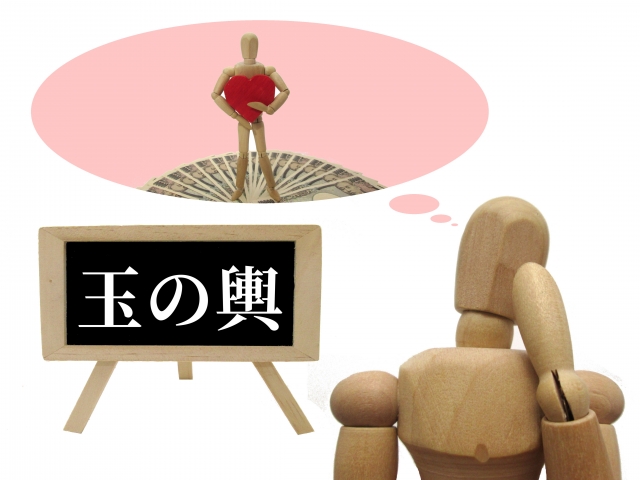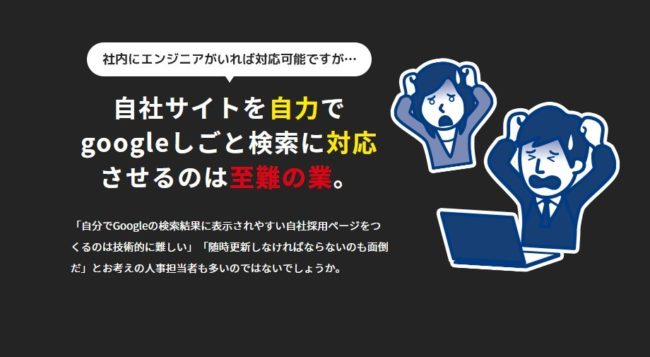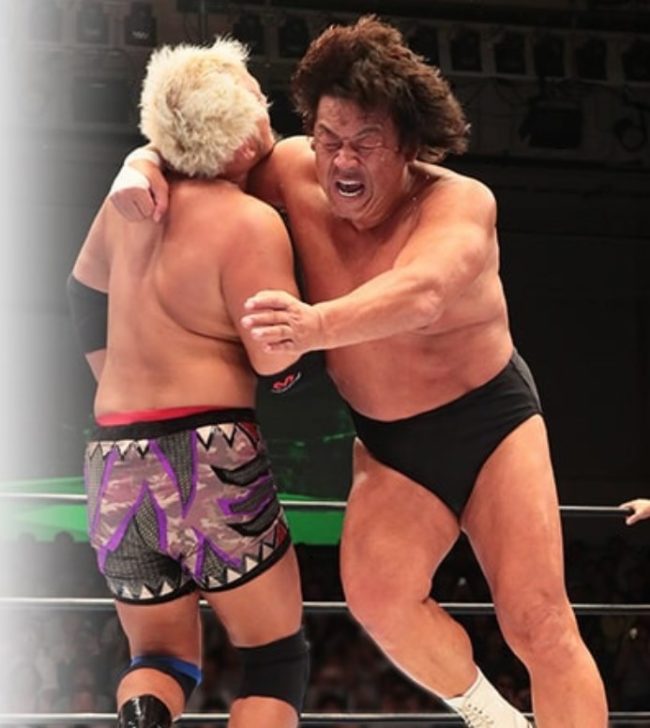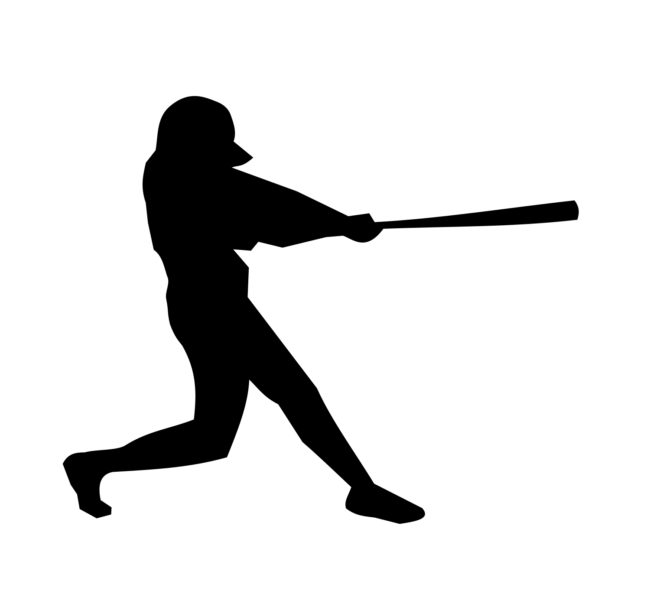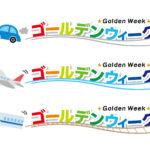一般的にはお金持ちの人をゲットして結婚した女性に「玉の輿に乗った」などと言いますし
最近では男性がお金持ちの女性と結婚した際に
「逆玉の輿に成功した」という風に聞くことがありますが
そもそも「玉の輿」の由来は何なのでしょうか?
よく聞く「玉の輿」の由来とされているのは?
諸説ありますが、多くの方は桂昌院のことを思い出す方が多いのではないでしょうか?
徳川3代将軍の家光の側室になってのちに5代将軍綱吉を産んだ桂昌院(お玉)が
側室になる前は京都の八百屋の娘だったところを見初められて大奥へ迎えられたとか…
将軍家から迎えに来たのは当然高貴な人が乗る「輿」だったわけで
お玉が輿に乗って栄達したということから「玉の輿」と言われていますね。

「玉の輿」の本当の語源や由来とは?
日本の話ではなく中国の話からという説が有力みたいですね。
中国の長編叙事詩「玉台新詠(ぎょくだいしんえい)」に書かれている
「孔雀東南飛(くじゃくとうなんひ)」という話が有力な語源だと言われています。
孔雀東南飛とは?
「玉台新詠」の中にある「焦仲卿(しょうちゅうけい)の妻の為に作る」という
お題の中の話が「孔雀東南に飛び・・・」という句から始まるので
その孔雀東南飛という話は後漢末期(200年前後)という時代の頃の話で
焦仲卿という下級役人の家に嫁いだ劉蘭芝(りゅうらんし)が
姑にイジメられ夫の焦仲卿を愛しているにもかかわらず実家に帰されてしまいます。
そして実家に帰ってきた劉蘭芝は親から無理やり再婚を迫られます。
当時は出戻りで独り者の娘がいるという事は世間体が良くなかったのかもしれませんが
嫌いで離婚したわけではなくむしろ元夫の焦仲卿を愛しているのです
そんな劉蘭芝の気持ちなどは無視して親は再婚する相手が上級官職だから
いい暮らしが出来るだろうとドンドン話を進め無理やり結婚の日取りを決めてしまいます。
絶望した劉蘭芝は愛する焦仲卿と寄りを戻せないくらいなら生きていても意味がないと
それを聞いた焦仲卿は愕然とし劉蘭芝の後を追うように木に首をくくってしまいました。
・・・という悲しい話なのです。
![]()
「玉の輿」の本当の意味は?
「玉台新詠」の中の孔雀東南飛で劉蘭芝が入水するときに懐に「玉」を入れていました。
この「玉」というのは八寸の玉で魂の身代わりとされこの世では結ばれなくても
あの世では結ばれるという魂を込めるという意味なのでしょう。
また「輿」というのは乗り物ではなく決心するとか願うという意味であり
まとめ
日本ではお玉こと桂昌院が栄達したきっかけになった輿に乗ってゆくということから
どちらも女性が関係することは同じですが全く意味が違いますね。
より印象的で魅力があると感じたので本当の語源由来だと思いたいです。
![]()